top of page
新刊
今年は「子どもの権利条約」が国連で採択されて30年です
ヤヌシュ・コルチャック(1878-1942年。本名ヘンリク・ゴールドシュミット)は、ポーランドが生んだ偉大な児童作家であり、小児科医であり、教育者です。子どもたちが衣食住を心配せずに 安心して過ごし、楽しく学べ、かつ家庭のようなあたたかさを持った場所を作ろうと、ユダヤ人の子どものための孤児院と、カトリックの子どものための孤児院を設立。子どもたちの父として生活をともにし、全生涯を子どもの教育と救済に捧げました。
また、教育書や新聞、童話、戯曲、ラジオ放送などを通して、世界のすべての子どもたちの福祉と権利を訴えました。子どもたちを尊重するという先生の夢は、死後47年を経て、コルチャック先生と孤児院の子どもたち国連の「子どもの権利条約」として実現しました。
コルチャック先生 関連図書
『コルチャック先生のいのちの言葉』
ヤヌシュ・コルチャック著、サンドラ・ジョウゼフ編著
(明石書店、2001年)
「子どもは未来ではなく、今を生きている人間である・・・」
コルチャック先生の子どもを見つめるあたたかい眼差しが心に響きます。

『コルチャック先生 子どもの権利条約の父』
トメク・ボガツキ作、柳田邦男訳
(講談社、2011年)
コルチャック先生の子どもたちへのあたたかい眼差しが伝わってくるような絵本です。コルチャック先生の生涯が分かりやすく綴られていて大人にもおすすめです。

『コルチャック先生』
近藤康子著
(岩波書店、1995年)
中学生から読めるコルチャック先生の伝記。第42回青少年読書感想文全国コンクール課題図書(高校の部)

おすすめ


Kokoroのおすすめ
『「ホロコーストの記憶」を歩く
~過去を見つめ未来へ向かう旅ガイド』
石岡史子 岡裕人著
(子どもの未来社、2016年6月)

メディアで
紹介されました

『エーディト、ここなら安全よ~ユダヤ人迫害を生きのびた少女の物語』キャシー・ケイサー著、石岡史子訳 (ポプラ社、2007年) ※小学校高学年から
ユダヤ人の子どもたちを守ったフランスの村モアサックを舞台にした実話。オーストリア生まれの少女エーディトは家族と引き離され、フランス南部の村の寄宿学校にかくまわれます。ナチスによるユダヤ人逮捕の危険が迫るたびに、村人たちはその情報を寄宿舎に届け、子どもたちはキャンプに出かけるふりをして山に隠れます。モアサックの村人たちの勇気によって、エーディトや500人を超える子どもたちの命が助けられました。わたしにだって、あなたにだって、きっとできることがある。そう思わせてくれる物語。

『あいつはトラだ!ベリゼールの はなし』ガエタン・ドレムス著、野坂悦子訳 (講談社、2010年) ※小学校高学年から
「あいつはトラだ!」の一言で、今まで友人だった相手への接し方を変えてしまうのが、私たち大人です。ためしに「あいつはトラだ!」の"トラ"の部分を変えてみればわかるでしょう。「あいつは○○だ」「あの人のお父さんは○○だから」・・・なんとなくイメージできたのではないでしょうか。
この本に出てくるベリゼールのようなトラの姿をした人間は、実在しません。でも、物語の中で大人がベリゼールに対してしたようなことは、周りを見渡してみれば、そこかしこで行われているのではないでしょうか。思い込みや先入観が生む悲劇に"われわれは敏感であるべきだ"。本書には、そんな作者のメッセージが込められています。
どうすれば私たちは、思い込みや先入観を捨てることができるのでしょう?子どもはベリゼールを恐れません。トラか人間かということは、子どもにとってどうでもよいことだからです。私たち大人に必要なのは、「あいつはトラだ!」と勝ち誇ったように言う者に対して、「どっちだっていいよ」と言える勇気なのではないでしょうか。大人にも読んでほしい本です。(ボランティア 東京都・教諭 山本)
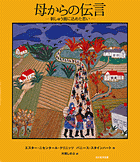
『母からの伝言 ~刺しゅう画に込めた思い~』エスター・ニセンタール・クリニッツ作、バニース・スタインハート作、片岡しのぶ訳 (光村教育図書、2007年)
ホロコーストの体験をこんなにかわいい刺しゅうで伝える方法があるのか!と本当に驚きました。美しくあたたかい刺しゅうが伝えるのは、15歳のときにポーランドで家族と離れて妹と隠れ潜み、友や隣人に家を追われ、森に逃げた恐ろしい体験。戦争以前の貧しくても平和だった我が家の思い出。終戦を待ちながらカトリック教徒として農家で働いたこと。夢の中で励ましを与えてくれた母やおじいさんのことなど。絵を勉強したことはなかった作者のエスターですが、50歳のときに思い立ち、娘時代の体験を語り伝えたいという願いを針と糸にたくしました。作者は2001年に74歳で亡くなりましたが、ここまで彼女の思いが近くに感じられるのは刺しゅうならではだと思います。あんまりきれいで、そして悲しくて涙がでてきます。(N.M.)

『忘却に抵抗するドイツ ~歴史教育から「記憶の文化」へ』岡裕人著 (大月書店、2012年)
「希望を育む記憶の文化」。この本をはじめて手にしたとき、帯に書かれていたこの言葉にとてもひかれました。ドイツがナチ時代の歴史と向き合い、繰り返し学び続けていることはよく知られています。それは、ドイツという今の国のカタチをつくっている「文化」の一つなのですね。でも、そこにたどりつくまでに、ドイツも苦しい道のりを歩んできたことが本書で分かります。最初から自国の負の歴史を直視できたわけではない。そのプロセスから私達が学べることは大きいのではないかと思います。
「忘れない」ということは、その記憶を様々な形で表現し、伝え、共有して、そこからより良い今と未来をつくりだそうということ。まさに「希望」につながるのですね。
小学生
小学生から読める本
『ハンナのかばん アウシュヴィッツからのメッセージ』カレン・レビン著、石岡史子訳 (ポプラ社、2006年)
『エーディト、ここなら安全よ ユダヤ人迫害を生きのびた少女の物語』キャシー・ケイサー著、石岡史子訳 (ポプラ社、2007年)
『おもいだしてください あのこどもたちを』チャナ・バイヤーズ・アベルス文、おびただす訳 (汐文社、2012年)
『わたしは千年生きた 13歳のアウシュヴィッツ』リヴィア・ビトン・ジャクソン著、吉澤康子訳 (日本放送出版協会、1998年)
『私を救ったオットー・ヴァイト ナチスとたたかった真実の記録』インゲ・ドイチェクローン著、藤村美織訳 (汐文社、2016年)
『コルチャック先生―子どもの権利を求めて』フィリップ・メリュ著、ペフ絵、高野優訳、坂田雪子訳、村田聖子訳 (汐文社、2015年)
『六千人の命を救え!外交官・杉原千畝』白石仁章著 (PHP研究所、2014年)
『ワレンバーグ−ナチスの大虐殺から10万人のユダヤ人を救ったスウェーデンの外交官』M.ニコルソン著、D.ウィナー著、日暮雅通訳 (偕成社、1991年)
絵本
『アンネの木』イレーヌ・コーエン=ジャンカ著、マウリツィオ・A.C.クゥアレーロ絵、 石津ちひろ訳 (くもん出版、2010年)
『国境を越えて 戦禍を生きのびたユダヤ人家族の物語』ウィリアム・カプラン著、千葉茂樹訳 (BL出版、2001年)
『エリカ 奇跡のいのち』ルース・バンダージー著、ロベルト・インノチェンティ絵、柳田邦男訳 (講談社、2004年)
『パパ・ヴァイト ナチスに立ち向かった盲目の人』インゲ・ドイチュクローン著、ルーカス・リューゲンベルク絵、藤村美織訳 (汐文社、2015年)
『コルチャック先生 子どもの権利条約の父』トメク・ポガツキ著、柳田邦男訳 (講談社、2011年)
『杉原千畝と命のビザ 自由への道』ケン・モチヅキ作、ドム・リー絵 (汐文社、2015年)
絵本
ホロコースト史
ホロコーストの歴史
『なぜ、おきたのか - ホロコースト』クライヴ・A・ロートン著、大塚信監修・訳、石岡史子訳 (岩﨑書店、2000年)
『ホロコースト』芝健介著 (中公新書、2007年)
『ヒトラーとナチ・ドイツ』 石田勇治著 (講談社、2015年)
『ホロコースト全史』マイケル・ベーレンバウム著、芝健介監修・訳 (創元社、1996年)
『ホロコーストを学びたい人のために』ヴォルフガング・ベンツ著、中村柳田邦男訳 (講談社、2011年)
『ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅 上・下』ラウル・ヒルバーグ著、望田幸雄ほか訳 (柏書房、1997年)
『ナチズム下の女たち 第三帝国の日常生活』カール・シュッデコプフ編著、香川檀訳 (未来社、1998年)
『ナチズム下の子どもたち 家庭と学校の崩壊』エーリカ・マン著、田代尚弘訳 (法政大学出版局、1998年)
『星をつけた子供たち ナチ支配下のユダヤの子供たち』デボラ・ドワーク著、芝健介監修、甲斐明子訳 (創元社、1999年)
生きぬいた人の証言
『夜と霧 新版』ヴィクトール・フランクル著、池田香代子訳 (みすず書房、2002年)
『アウシュヴィッツは終わらない あるイタリア人生存者の考察』プリーモ・レーヴィ著、竹山博英訳 (朝日新聞社出版局、1980年)
『夜 新版』 エリ・ヴィーゼル著、村上光彦訳 (みすず書房、2010年)
『運命ではなく』イムレ・ケルテース著、岩﨑悦子訳 (国書刊行会、2003年)
『私はガス室の「特殊任務」をしていた』シュロモ・ヴェネツィア著、鳥取絹子訳 (河出書房新社、2008年)
『アウシュビッツを一人で生き抜いた少年』トーマス・バーゲンソール著、池田礼子訳、渋谷節子訳 (朝日新聞出版、2012年)
『エヴァの時代 アウシュヴィッツを生きた少女』エヴァ・シュロッス著、吉田寿美訳 (新宿書房、 2000年)
証言
助けた人たち
ユダヤ人を助けた人たち
『私はシンドラーのリストに載った』エリノア・ブレッチャー著、幾野宏訳 (新潮社、1996年)
『ユダヤ人を救った動物園 ヤンとアントニーナの物語』ダイアン・アッカーマン著、青木玲訳 (亜紀書房、2009年)
『ユダヤ人を救った外交官 ラウル・ワレンバーグ』 ベルント・シラー著、中村哲夫訳、田村光彰訳 (明石書店、2001年)
『イレーナ・センドラー ホロコーストの子ども達の母』平井美帆著 (汐文社、2008年)
アンネ・フランク
『アンネの日記 増補新訂版』アンネ・フランク著、深町眞理子訳 (文藝春秋、2003年)
『アンネ・フランク その15年の生涯』黒川万千代著 (合同出版、2009年)
『思い出のアンネ・フランク』 ミープ・ヒース著、深町眞理子訳 (文藝春秋、1987年)
『アンネ・フランク最期の七カ月』ウィリー・リントヴェル著、酒井府訳、酒井明子約 (徳間書店、1991年)
『アンネ・フランクの記憶』小川洋子著 (角川書店、1998年)
アンネ・フランク
杉原千畝
杉原千畝
『六千人の命のビザ』杉原幸子著 (大正出版、1994年)
『決断・命のビザ』渡辺勝正、杉原幸子著 (大正出版、1996年)
『杉原千畝 情報に賭けた外交官』白石仁章著 (新潮社、2015年)
『六千人の命を救え!外交官・杉原千畝』白石仁章著 (PHP研究所、2014年)
歴史と向き合うドイツ
『忘却に抵抗するドイツ - 歴史教育から「記憶の文化」へ』岡裕人著 (大月書店、2012年)
『ドイツは過去とどう向き合ってきたか』熊谷徹著 (高文研、2007年)
ドイツ
本棚
bottom of page








